Nintendo 家庭用ゲームハードの歴史 前編
皆さんこんにちは、かんてい局南高江店です。
今日は先日のプレイステーションに続いて
ゲームは言えばの任天堂。
始まりは1889年の京都、手作りの花札からスタートした。
そこから誰でも知ってるゲーム会社へと成長していった。
今回はその任天堂さんが発売した家庭用ゲームハードについてまとめていきます。
カラーTV ゲーム6(1977)
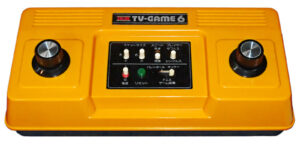
1970年代後半、家庭のテレビで遊ぶ“卓上ゲーム機”市場が世界的に拡大。
任天堂は 1977年、9,800 円の『カラーTV ゲーム6』で参入し、翌年には15タイトル版やレースゲームなどが登場。
中でもブロック崩しが行えるものだったそうです。
ゲーム&ウオッチ(1980)


1980年に任天堂から発売された携帯型ゲーム機。
1台に1つのゲームが内蔵されており、ゲームをしない時は時計機能としても使えることから、この名が付けられました。
1981年『ドンキーコング』版は十字キーの原型を生んだ。
ファミリーコンピュータ(1983)

1983年に8bit機『ファミコン』が日本で発売。
安価なカートリッジ交換式と3色線グラフィックで家庭用タイトル開発を加速させ、
1985年北米で『NES』として展開しテレビゲーム不況を立て直した。
当初は37タイトルしかなかったものの、最終的には1,000本以上のソフトが発売され、
国内で約1,935万台、世界では約6,000万台を販売。
「ゲーム=任天堂」という時代を築いた伝説的ハードです。
ファミコンの登場は家庭用ゲームに革命をもたらしました。
ゲームボーイ(1989)
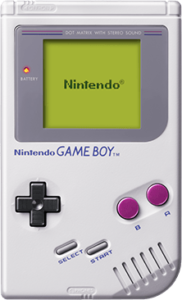
1989年、任天堂は携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を発売。
ポケットに入るサイズで、どこでも遊べる夢のような体験を提供しました。
代表作は『テトリス』『ポケットモンスター 赤・緑』など。
後者は社会現象となり、世界中でポケモンブームを巻き起こします。
→ 世界累計販売台数は1億1,800万台(カラー含む)。
携帯ゲーム市場を切り拓いた、もう一つの伝説です。
スーパーファミコン(1990)

ファミコンの後継機として登場。
当時としては驚異的な16ビットCPUを搭載し、より美しいグラフィックと立体的なサウンドを実現。
モード7と呼ばれる回転・拡大縮小機能によって、擬似3D表現も可能になりました。
Virtual Boy(1995)

バーチャルボーイは世界初の裸眼3D表示を謳ったが、赤単色LEDと据置型の中途半端さで1年足らずで終息。
Nintendo 64(1996)

1996年『N64』はカートリッジ高速ロードを維持しつつ、
アナログスティック+振動パックで3D空間操作を一般化。
『スーパーマリオ64』『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、
3Dゲームデザインの教科書とされる名作です。
ゲームボーイカラー(1998)
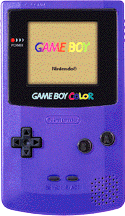
ゲームボーイの名を継ぎながら、カラフルなゲーム体験を実現。
『ポケモン 金・銀』などで再び大ヒット。
今回はここまで!やはりゲームを作ってきたNintendoですね。続きは明日!

