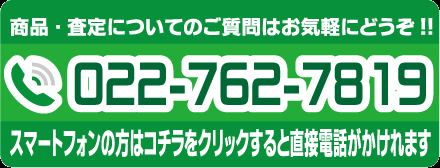【3月3日は何の日?】雛祭り・桃の節句
♦目次♦
今日は3月3日、雛祭りです。
今回はいつぞや 後回しにした”節句”と雛祭りについて、ざっくり解説していきます。
期間限定キャンペーン
開催中

3月3日は何の日?
3月3日はひな祭り、桃の節句です。5月5日の端午の節句=男の子の日(≠こどもの日)に対して、女の子の日とも呼ばれますね。節句としての和名は「桃の節句」あるいは「雛の節句」であり、漢名では「上巳(じょうし)」と呼ばれます。
ちなみに、こどもの日はその名の通りこどもの日です。ですので、こどもの日”は”男の子の日ではありません。というのも、元々は3月3日・桃の節句(=女の子の日)と5月5日・端午の節句(=男の子の日)を掛け合わせて5月3日としようとする案があったのです。が、5月3日は憲法記念日になったため、「じゃあ時季の良い5月5日にしよう」となりました。つまり、元々端午の節句があるところにこどもの日も入り込んできた形になります。[1] 5つある節句の中で端午の節句の日だけが祝日なのも、これが原因。
”節句”とは?
季節を分ける日[2]……の前日が節分なのに対して、節句は年中行事を行う、各季節の節目になる日を指します。1月~9月の奇数月で、1月以外は月と日が同じ数字になる暦であり、それぞれ
- 日付 漢名 和名
- 1月7日 人日(じんじつ) 七草の節句
- 3月3日 上巳(じょうし) 桃の節句・雛の節句
- 5月5日 端午(たんご) 端午の節句・菖蒲(しょうぶ)の節句
- 7月7日 七夕(しちせき) 七夕(たなばた)[3]・笹の節句
- 9月9日 長陽(ちょうよう) 菊の節句
と、なります。1月1日=元旦が節句でないのは、「一年の始まり」ということで季節の節目とは格が違うためです。
なお、節句の原型の一つとして節会(せちえ)という朝廷主催で節日に行われる宴会があり、こちらは
- 1月1日 元日節会
- 1月7日 白馬節会
- 1月16日 踏歌節会
- 3月3日 上巳節会
- 5月5日 端午節会
- 7月7日 相撲節会
- 9月9日 長陽節会
- 11月23日? 豊明節会
- 以下略
と、節句よりも数が多いものでした。これに中国の五行説[4]の影響などなんやかんやあって、今の五節句に落ち着きました。
なお、上巳の節句が桃の節句とも呼ばれるようになったのは、旧暦3月3日頃は桃が咲き始める時期だから……なのですが、時期が1ヶ月ほどズレる新暦だと桃が咲く季節ではないため、基本的に桃の造花が使われます。
雛祭りの原型?
雛祭りの起源は古く、平安時代より前から行われていた「上巳の節句」と言われております。これは、上流階級の子女が御所[5]を模した御殿[6]や飾りつけで遊ぶことで、健康や厄除けを願うものでした。上代日本人版シルバニアファミリー
このように最初は貴族の催しでしたが、(鎌倉時代から?)武家でも行われるようになり、江戸時代には庶民の人形遊びと結びつくなどして発展しました。ほかにも、元々の目的の一つである「厄除け」祈願として、「人形に穢れを移し、それを川や海などに流す」いわゆる流し雛(或いは雛流し)もありました。
なお、どうにも文献が見つからないので憶測にはなりますが、成立順は
- 流し雛(上巳に行うのは中国文化、催し自体は日本神話発?[7])
- 上巳の節句
の上代日本人版シルバニアファミリー - 鎌倉~安土桃山時代、武家も実施
- 江戸時代から、現代に近しいもの
と、変遷したものと考えられます。
ところで、元々は端午の節句ともども男女分け隔てない祝い事として扱われていたのですが、江戸時代から「(人形を飾る)雛祭りは女子」「端午の節句は男子」と分かれたのでした。
ちなみに、流し雛に似た風習は中国にもありますが(というより恐らく中国の風習が原型)、雛人形を飾るのは日本特有の文化です。
最後に
そんなわけで、今日はひな祭りです。
五行思想やら四元素やらの小難しい解説についてはまたの機会に。(●’◡’●)
注釈
[1]^ 内閣府ホームページ・各「国民の祝日」について・こどもの日(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou/kaku.html#kodomo)
[2]^ 立春・立夏・立秋・立冬のこと。(【2月3日は何の日?】)
[3]^ 仙台七夕まつりは月遅れの8月6日・7日・8日に実施されます。理由としては、梅雨明け後だった旧暦の7月7日と違い、グレゴリオ暦=新暦の7月7日だと梅雨の真っただ中になってしまうため。それの何が不都合なのかと言うと、吹き流し(=飾り)が濡れてグズグズになる伝説に曰く、「七夕の日に雨が降ると天の川が増水して橋が架けられなくなってしまう」のだとか。要するに、年に一度の逢瀬の日なのに(毎年ほぼ確定で)織姫と彦星が逢えなくなってしまうため。
[4]^ ごぎょうせつ、或いは五行思想(ごぎょうしそう)。主に古代中国や、その文化を取り入れた日本などで用いられていた自然哲学のこと。万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなるとしています。五芒星(円の中に星マークが描かれているアレ)で表されます。ちなみに、西洋では火・空気(または風)・水・土からなる四大元素でした。なお、”万物”の表現からわかるように、現代化学でいう「原子」とは異なり、物質の組成だけでなく物事の性質といった分野も全て五行・四元素で考えられておりました。これ以上は長くなりますので割愛。
[5]^ ごしょ。天皇や、高い身分の貴族の住む邸宅。もしくは、天皇そのものを指すことも。御所に限らず日本の場合、身分の高い人が住む建物をそのまま呼び名・敬称として用いる事が多々あります。大御所、殿、お館様、公家などもその一つ。
[6]^ ごてん。身分の高い人が住む邸宅のこと。御所よりはランクが下になります。
[7]^ 古事記に曰く、国生みと神生みの男神《伊邪那岐命》(イザナギノミコト)・女神《伊邪那美命》(イザナミノミコト)の二柱の間に最初に生まれた《蛭子》(ヒルコ)という神様が居たのですが、不具に生まれてしまったため、船に乗せて流されてしまいました。そこから転じて穢れを払うための……となるのですが、今の世の中コンプライアンス的に刺されそうですね。[ここから大幅に脱線]なお、古事記においては蛭子は以後登場しません。ところで兵庫県西宮市にある西宮神社は全国各地にある「えびす神社」の総本社なのですが、この神社の主祭神は《えびす大神》……《蛭児命》(ヒルコ)となっております。表記こそ異なりますが蛭子のことです。なんでも、神戸沖に流れ着いた蛭子を西宮市の人々が保護したんだとか。で、夷(えびす:(未開の)異民族という意味。ただし、大元である蝦夷(えみし)はあまり好ましい意味の単語ではない)と呼んで大事にしていたそう。その結果、漁業や航海のご利益があったとかなんだとか。その後七福神の恵比寿と同一に扱われるようになるなどして、今に至ります。七福神やそれと(信仰的な意味で)合体した神々についてのざっくり詳しいお話は、また別の機会に。(●’◡’●)
かんてい局 仙台卸町店について
ルイヴィトン、ロレックスなど
ブランド品の高額査定を行っております!
ウイスキー、ブランデー、シャンパンなど
お酒の高額査定も行っております!
定番商品から限定品まで
なんでも買取りしております!
お時間が空いた時など気軽にお立ち寄りください。
◆ かんてい局店仙台卸町店
宮城県仙台市若林区大和町5丁目1-15
営業時間:10:00~19:00
※査定受付は18:45迄
第二水曜定休
★LINE始めました★お友達登録をお願いします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
↑↑↑↑↑↑↑↑